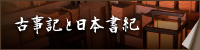『古事記』の成り立ち
『古事記(こじき)』が完成したのが712年(和銅5)。
太安万侶(おおのやすまろ)の序文(じょふん)には、
天武天皇(てんむてんのう)が、
舎人(とねり)の稗田阿礼(ひえだのあれ)に命じて
誦み習わせた帝紀(ていき)と旧辞(きゅうじ)を、
天武天皇の没後に、元明天皇(げんめいてんのう)の命令で、
太安万侶が撰録(せんろく)し、
712年に進上した、と記されています。
帝紀とは、歴代の天皇の系譜。
旧辞とは、古い時代に、
各地の氏族に口誦で伝えられた様々な伝承のこと。
その系譜や伝承が、
一つの大きな物語として体系化されたのが、
天武天皇の即位後の7世紀後半ごろ。
その体系化された物語が、
日本の「歴史」として、文字に記録され
元明天皇に進上されたのが712年になります。
現存する最古の歴史書
710年に都が藤原京(奈良県橿原市)から奈良の平城京に移されました。その2年後の712 年、太安万侶(おおのやすまろ)によって『古事記』がまとめられました。これは、7世紀後半の天武朝に天皇の命を受けて、稗田阿礼(ひえだのあれ)が習誦していた歴史を太安万侶が筆録したものです。日本の歴史を叙述したものとしては現存最古であり、日本の古代史を語る際には欠かすことのできない根本史料です。
神話が重視されている
『古事記』は、神代から推古天皇までを紀伝体で記述しています。上・中・下巻の3巻から成っていて、このうちの上巻は神代にあてられており、神々の世界が描かれています。具体的には、天地開闢から始まって天孫降臨に至るまでが叙述されています。このように上巻の出だしは天地が分離したことから始まっているわけですが、太安万侶が記した序文では、天地が未分離の状態から書き始められています。
しかし、いずれにしてもここから言えるのは、神話の比重が大きいこと。このことは神代の昔から葦原中つ国(地上の国)の支配者は天皇家であるということを強調していると思われ、ここにこそ『古事記』の最大の編纂意図があると言ってよいでしょう。 中巻は神武天皇から応神天皇までが記されています。この時代は、神武天皇の東征伝承や神功皇后のいわゆる三韓平定伝承などをみてもわかるように英雄的な天皇が多く登場します。
下巻は聖帝伝承で有名な仁徳天皇から推古天皇までのことが記されていますが、最後のほうになると記述がとても簡単になっていて、有名な聖徳太子の伝承などはほとんど記されていません。