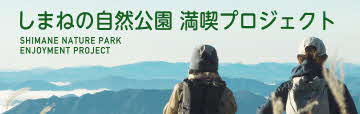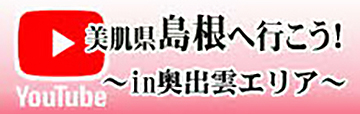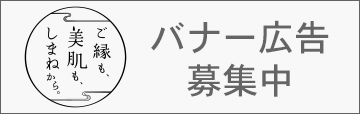石見地方のやきものめぐり(3)
2016年04月19日 公開
石見焼の窯元を訪ねよう
江津市(ごうつし)一帯に窯元が点在する石見焼。
「はんどう」と呼ばれる大きな水がめの産地として、大物をつくる技術が磨かれてきました。
高い技術力を生かした、暮らしに寄り添ううつわはいまも健在です。
江戸時代の宝暦年間(1751~1764)から本格的に生産が始まったとされている石見焼。窯元を訪ねると、窯や工房の片隅にかつて盛んにつくられていたはんどうの実物を見ることができます。
前回の記事はこちらから
≫ 石見地方のやきものめぐり(2)
石見焼を象徴する「はんどう」

来待石の釉薬に、黒い打ち掛けの文様をつけただけの、いかにも堅牢な大型のかめ。写真に写っているのは、のちに紹介する宮内窯でつくられたはんどうです。大人の胸ほどまでに達するかめの姿を実際に目にすると、その大きさにあらためて驚きます。こうした大型のやきものは一気にはろくろでひくことができません。そこで生まれたのが、「しのづくり」と呼ばれる石見焼伝統の技法でした。
しのづくりは、太い紐状の粘土をろくろの上に円を描くように積みあげたのち、ろくろをまわして平らにならしていきます。半乾きになったところで粘土を積みあげることを何度か繰り返し、目指す大きさまでもっていきます。粘土の収縮具合を考えながら、継ぎ目なくつくりあげていくには腕力とともに、熟練の技をも要します。大物の製作にも耐えうる良質な陶土と、大物をつくる職人の高い技術力とに支えられ、石見焼の名は全国に知れ渡ることになりました。
石見焼の窯元は、粘土が産出する近くに築かれてきたため、点在しています。今回は2つの窯元をご紹介しますが、毎年秋に開かれる「石見大陶器市」では窯元一同が勢揃いします。その際に、お気に入りの窯元を探すのもおすすめです。
石州嶋田窯


1935(昭和10)年に開窯した嶋田窯。その庭のところどころに、陶製の階段の柵やポストなど、遊び心に富んだやきものが置かれています。

これらはお話を伺った3代目・嶋田孝之さん作のもの。伝統工芸士である孝之さんは大物づくりを得意としていますが、ふだんは4代目の健太郎さんとともに、食器類を中心に作陶しています。1995年からは長く使っていなかった登り窯にふたたび火を入れるようになり、現在では年に5回焚いています。
ゴールデンウィークの毎年5月3日~5日は「登り窯祭り」を開催。まだあたたかいやきものを手に取れるとあって、いまや大勢のファンが集まるイベントになっています。


石州嶋田窯
〒699-2841 島根県江津市後地町1315
TEL:0855-55-1337
【開館時間】9:00~17:00
【休館日】不定休
石州宮内窯


宮内窯は、伝統工芸士で2代目を務める宮内孝史さんの父・謙一さんが1970(昭和45)年に開いた窯。同じく伝統工芸士で、大物づくりの名人として知られる謙一さんの技術を受け継ぎ、傘立てや睡蓮鉢などの大きなものから蓋つき壺やすり鉢まで、「現代の暮らしにあう形を考えながらつくっています」と孝史さん。


広々とした販売スペースには、ちょっとした漬物を入れるのによさそうな蓋つきのシンプルな壺をはじめ、大小さまざまなやきもので埋め尽くされています。なかでもすり鉢やおろし皿は、手仕事によって生まれる不均一さが、食材のおいしさを引き出すと評判。いますぐキッチンに取り入れてみたいうつわがずらりと並んでいます。


石州宮内窯
〒695-0024 島根県江津市二宮町神主2211-3
TEL:0855-53-0304
【開館時間】:8:00~17:00
【休館日】不定休
関連記事はこちらから
≫ 石見地方のやきものめぐり(1)
≫ 石見地方のやきものめぐり(2)