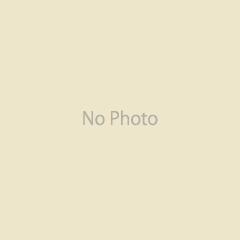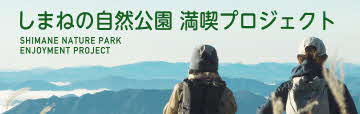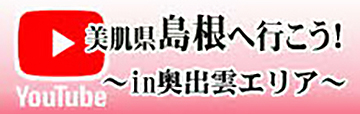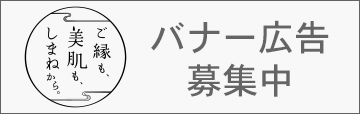ゴトバジョウコウ
後鳥羽上皇
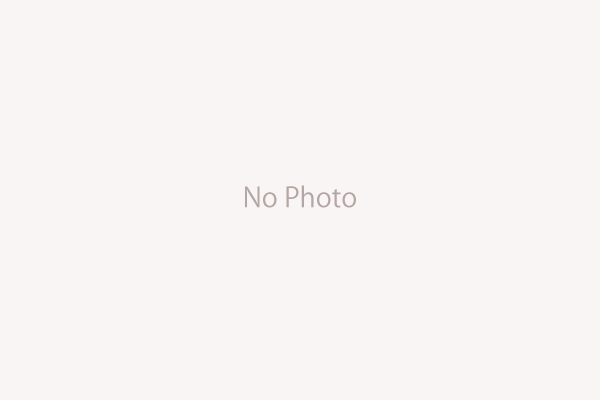
高倉天皇の第四皇子として、治承4年(1180)に生まれた。3歳のとき平氏が安徳天皇を伴って都落ちしたため、祖父後白河院の詔によって践祚(せんそ)した。皇位の象徴である三種の神器は平氏が持ち去っていったため、神器なしの異例の践祚であった。建久9年(1198)皇子である土御門天皇に譲位し、上皇として院政を始めた。こののち土御門、順徳、仲恭天皇の三代23年にわたり御鳥羽院の院政が続けられた。この間、西面(さいめん)の武士を設置するなど朝権の回復を図ることに努めた。
鎌倉幕府の三代将軍源実朝の死後、院と幕府北条氏との対立は激化し、ついに承久3年(1221)執権北条義時追討の院宣を諸国に下し挙兵、承久の変が起こった。しかし幕府の大軍はたちまち京都を占領し、院方の完敗に終わった。後鳥羽院の広大な領地は殆んど没収され、さらに後鳥羽院は隠岐島に配流された。それより在島19年、幕府の監視下で側近の男女数名と、望郷の思いに身を焦(こ)がしながらわびしい生活を送った。「われこそは 新島守よおきの海の荒き波風心して吹け」「蛙鳴く刈田の池の夕だたみ 聞かましものは松風の音」などの歌に、上皇の心境をうかがうことができる。
このわびしい毎日を慰めるため、上皇は和歌にうち込み、刀剣鍛冶に興味をもち、そして阿弥陀の救済にたよって念仏を唱えた。中でも和歌の道における業績はすばらしく、『新古今和歌集』の改訂、『遠島御百首』『遠島御歌合』『後鳥羽院御自歌合(おんじかあわせ)』の興行など和歌文学史上特筆すべきものである。
上皇は延応元年(1239)2月22日、勝田山源福寺(かったさんげんふくじ)(隠岐郡海士町)の行在所で60歳の悲運の一生を終えられた。